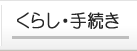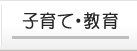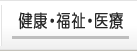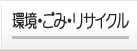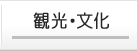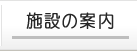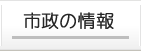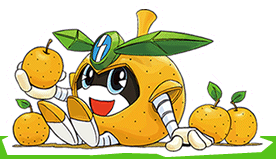令和6年度の献立
更新日:2024年7月3日
令和6年6月27日(木曜日)の給食
タッカルビ丼
6月の世界の料理は、日本から近い場所にある国の韓国です。
タッカルビは韓国の焼肉料理の一つで、「タッ」は鶏、「カルビ」はあばら骨を意味します。鶏肉やキャベツ、玉ねぎなどの野菜を韓国のみそ、コチュジャンで炒めた料理です。チーズをトッピングした「チーズタッカルビ」も有名です。
給食では、ご飯にかけた「タッカルビ丼」でいただきました。

6月27日の給食
令和6年6月13日(木曜日)の給食
ひきないり
今月のご当地給食は福島県です。
ひきないりは福島県で食べられている郷土料理の一つです。「ひきな」とは福島県の方言で大根などの野菜を千切りにしたものを表し、「ひきな」を炒めた料理を「ひきないり」と呼びます。冬場のために千切りにして保存した野菜で作られた料理と言われていて、昔から家庭料理として親しまれてきました。
使用する食材や味付けは家庭によって様々ですが、給食では大根のほかに鶏肉やちくわ、人参、ピーマンを使用し、砂糖やしょうゆなどで甘辛く味をつけました。

6月13日の給食
令和6年5月29日(水曜日)の給食
ウインナートマトソース
5月の世界の料理は、アルゼンチンです。
アルゼンチンは、南アメリカ大陸の南東部に位置する国です。ジャングルや大草原など大自然に恵まれたことから農業や牧畜業が盛んに行われるようになりました。特に肉をよく食べる食文化で、一人当たりの肉の消費量は世界トップクラスです。
チョリパンは、チョリソーと呼ばれる太いソーセージをパンに挟んだ料理です。チミチュリと呼ばれる、酢と香辛料から作られるソースをかけて食べることもあります。今回の献立は、コッペパンにトマトソースをからめたソーセージを挟んでチョリパン風に仕上げました。

5月29日の給食-1

5月29日の給食-2
令和6年5月27日(月曜日)の給食
さわらの西京みそだれ
5月のご当地給食は京都府です。
みそは、大豆や米、麦などの穀物に塩と麹を加えて作る発酵食品で、日本の伝統的な調味料の一つです。日本各地で作られていて、地域によって材料や風味、色にそれぞれ特徴がある、地域色の強い食品です。西京みそは、江戸時代に京都で誕生し、現在も京都で作り継がれている、色が淡く、甘味があるのが特徴の白みその一つです。「西京みそ」という名前は、明治維新によって江戸が「東京」と名前を変えたため、西の都である京都を「西京」と呼ぶことになったことから付けられました。
今日の給食では、西京みそでたれを作り、焼いたさわらにかけました。

5月27日の給食
令和6年4月30日(火曜日)の給食
豆乳仕立ての飛鳥汁
4月のご当地給食は奈良県です。
飛鳥汁は、牛乳や鶏肉、季節の野菜が入ったみそ仕立ての汁もので、奈良県の伝統料理です。飛鳥時代に中国の旧王朝である唐から牛乳と鶏肉料理が伝わり、貴族の間で食べられていたと言われています。
今日の給食の飛鳥汁は、牛乳の代わりに豆乳を使いました。豆乳と味付けに使ったみそは、どちらも大豆からできているので相性が良く、まろやかな味わいになります。

4月30日の給食
令和6年4月19日(金曜日)の給食
スコッチブロス
今月の世界の料理は、イギリスです。
スコッチブロスは、イギリスのスコットランドで有名な料理で、肉や野菜、大麦などを入れて煮込んだ具だくさんのスープです。本場では羊や牛の肉を使うことが多いですが、給食では豚肉を使って作りました。
スープに使用した麦は「押麦」と言って、蒸した大麦を押しつぶして乾燥させたものです。おなかの調子を良くする食物繊維が豊富で、プチプチとした食感を楽しむことができます。

4月19日の給食
このページについてのお問い合わせ
稲城市 教育部 学校給食課
東京都稲城市矢野口3648番地
電話:042-377-8904 ファクス:042-379-1501