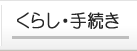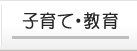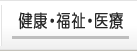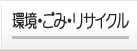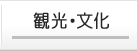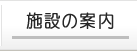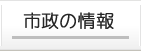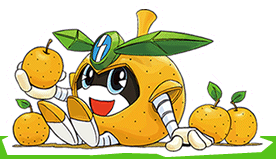高額療養費
更新日:2024年4月1日
病気やけがで病院にかかり、医療機関で支払った月ごとの一部負担金(注釈)が自己負担限度額を超えた場合は、その差額を市が高額療養費として支給します。
対象となる場合、原則として診療月の3か月後に世帯主へ申請書をお送りしますので、申請書が届いたら郵送もしくは市役所または出張所の窓口で申請してください。
注釈: 保険適用外の費用(文書料、入院中の食事代、差額ベッド代など)については、高額療養費の対象にはなりません。
高額療養費の申請に必要なもの
- 市から送付された申請書
- 印鑑
- 通帳など、振込口座がわかるもの
- 本人確認書類
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
高額療養費を支給する際、国民健康保険税の未納分に充当する場合があります。
郵送申請の場合は、必要事項を記入し、押印をした申請書をご返送ください。
高額療養費の自動振り込みができるようになりました
これまで高額療養費の支給を受けるには、該当月ごとに申請手続きをする必要がありましたが、ご希望により自動振り込みができるようになります。
自動振り込みの申請方法
高額療養費支給申請書の「自動振り込み希望欄」にチェックを入れてご申請ください。
一度口座を登録していただくと、2回目以降は申請手続きが不要となり、市から指定口座に自動的に振込みをします。振込の際には高額療養費支給決定通知書を送付いたします。
自動振り込みの対象とならない場合
次のような場合には自動振込が解除されます。改めて支給申請書をご提出ください。
- 転出、世帯分離等による世帯構成の変更があった場合
- 口座解約等で指定された口座への振込ができなかった場合
- 保険税の滞納がある場合
- 病院での支払いが済んでいない場合
注意事項
- 過去に申請書を送付した分については、今までどおり申請書を提出する必要があります。
- 自動振込みの申請後は、高額療養費支給申請書は送付されません。
- 支給金額や振込日等は、支給決定通知書でご確認ください。
高額な医療費がかかることが、あらかじめ分かっている時
入院または外来などで高額な医療費がかかるときは、「限度額適用認定証」等を医療機関に提示すると、1か月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
医療機関(入院・外来別)、薬局それぞれでの計算となるため、同月に複数の医療機関等での受診がある場合は、高額療養費の申請が必要になることがあります。
「限度額適用認定証」等の手続き
70歳以上の方については、課税所得145万円以上690万円未満の現役並み所得者と、住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証が必要となりますので申請してください。
それ以外の現役並み所得者(課税所得690万円以上)と、一般の区分にあたる70歳以上の方については、医療機関へ高齢受給者証を提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額までの窓口負担となりますので、限度額適用認定証は不要です。
「限度額適用認定証」等の手続きに必要なもの
注釈:1 平尾・若葉台出張所で手続きした場合は、郵送します。
注釈:2 国民健康保険税に未納がある方には交付できません。
マイナンバーカードを保険証として利用する場合
マイナンバーカードに健康保険証利用の登録をされていて、オンラインで医療保険資格の確認ができる医療機関を利用する場合、「限度額適用認定証」等の提示は不要です。
自己負担限度額について
70歳未満の方の自己負担限度額
| 区分 | 所得要件 (総所得金額等-43万円) |
1か月の自己負担限度額 |
|---|---|---|
| ア | 901万円を超える世帯 または、所得未申告世帯 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
| イ | 600万円超 901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
| ウ | 210万円超 600万円以下の世帯 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
| エ | 210万円以下の世帯 | 57,600円 <多数回該当:44,400円> |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 <多数回該当:24,600円> |
- 医療機関ごとで、一部負担金が月に21,000円以上となったものを合算した額が、上記の自己負担限度額を超えた場合に、差額を支給します。
- 入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 薬局分は、処方した医療機関分と合わせて、月に21,000円以上となったものが合算対象となります。
- 「多数回該当」とは、療養のあった月を含む過去12か月間に一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降に適用される自己負担限度額です。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
| 所得区分 | 1か月の自己負担限度額 外来(個人ごと) |
1か月の自己負担限度額 外来+入院(世帯ごと) |
|
|---|---|---|---|
| 現役並み3 | 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <4回目以降:140,100円(注釈4)> |
|
| 現役並み2 | 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <4回目以降:93,000円(注釈4)> |
|
| 現役並み1 | 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <4回目以降:44,400円(注釈4)> |
|
| 一般(注釈1) | 課税所得 145万円未満 |
18,000円 <年間(8月から翌年7月)上限144,000円> |
57,600円 <4回目以降:44,400円(注釈4)> |
| 低所得者2(注釈2) | (注釈3) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1(注釈2) | (注釈3)及び所得が一定基準以下 | 8,000円 | 15,000円 |
注釈1:世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書き所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
注釈2:住民税非課税世帯の方については、従来どおり。限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
注釈3:世帯主と国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税の世帯。
注釈4:過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方を合算するとき
- 70歳以上75歳未満の方の外来(個人単位)の限度額をまず適用
- それに入院も含めて70歳以上75歳未満の方の世帯単位の限度額を適用
- これに70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担限度額)を加えて、70歳未満の方の限度額を適用
手続き可能日時
開庁日の午前8時30分から午後5時
備考:休日開庁日は、午前8時30から正午、午後1時から午後5時
注意:休日開庁は市役所のみです。
外来年間合算
外来診療で自己負担の年額(8月から翌7月までの1年間)の合計額が144,400円を超えた場合に差額を支給します。対象となる可能性がある世帯には1月から2月頃に通知と申請書を発送します。
対象
次のすべてに該当する方
- 7月31日時点で国民健康保険に加入しており、70歳以上の方
- 7月31日時点の所得区分が「一般」「低所得者2」「低所得者1」の方
このページについてのお問い合わせ
稲城市 市民部 保険年金課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781