江戸の里神楽(さとかぐら)
穴沢天神社の祭礼について
令和元年の穴沢天神社の祭礼は、8月25日(日曜日)です。
江戸の里神楽は午後1時ごろから、穴沢天神社内の神楽殿にて見ることができます。

神楽と江戸の里神楽の歴史
神楽は古代に発生した芸能で、民俗芸能の中では最も古い歴史をもつと言われます。その起源は、神霊を慰めるために演じたもので、神に捧げる舞踊でした。「神を招き迎えたときの神霊の依りたもう座」を意味する神座という言葉が、神楽の語源と考えられます。
古代に発生した神楽は、江戸時代初期には江戸市中に伝わり、江戸庶民の好みに応じて、いろいろな形に変化します。その一つが江戸の里神楽で、江戸と周辺の村々の神社の祭礼などで盛んに里神楽が奉納されました。この江戸の里神楽の特徴は、仮面を付けた黙劇であり、神話の世界を題材としたものを中心に演じられたことです。また演じる人たちが専業の神楽師であったこともあげられます。
現在都内には、四つの江戸の里神楽が伝承されています。間宮社中(品川区)、若山社中(台東区)、松本杜中(荒川区)と稲城市の山本杜中です。四社中とも国の重要無形民俗文化財に指定されています。
稲城の江戸の里神楽
山本頼信社中の江戸の里神楽は、初代の山本権律師弘信が室町時代初期の応安6年(1373年)に創始したといわれ、現在の家元山本頼信氏は十九代に当たります。山本家の近くにあった国安神杜で神楽を舞ったのが始まりと言われ、『江戸名所図会』(天保7年刊)には、国安神社と仮殿・社人の建物が描かれ、この仮殿として描かれた建物が、祈祷殿としての機能をもち、諸事の祈祷や神楽を舞う場所として使われたのではないかと考えられます。
山本家には江戸時代中期の写本と思われる『神事式名録』という神楽の台本のほかに、明和6年(1769年)に記された『岩井神杜鈴森御神楽格式』という古文書(神楽の演目と持ち物・形相を記載)など数々の資料が残っています。これらの資料により、江戸時代から現在に至るまで里神楽が綿々と受け継がれてきたことがわかります。また江戸時代中期頃で50座の里神楽が演じられていたことが記録されています。
江戸の里神楽の演目
現在、山本頼信社中では、40数座の里神楽を演じていますが、その中の代表的な演目は次のとおりです。
- 〔古典もの〕 天之浮橋、黄津醜女、墨江大神、八雲神詠、天之磐扉、剣玉生神、神遂蓑笠、天之返矢、幽顕分界、天孫降臨、笠沙桜狩、山海幸易、妖賊剪滅、三輪神杉、狭穂討伐、熊曽征伐、東夷征伐、酒折連歌、兄弟探湯、億兆豊楽、敬神愛国、三穂崎漁釣
- 〔近代もの〕 紅葉狩
- 〔お伽とぎもの〕 稲葉の素兎

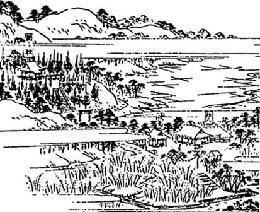


より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市郷土資料室
〒206-0823 東京都稲城市平尾1-9-1
電話番号:042-331-0660 ファクス番号:042-331-0660
稲城市 教育部 生涯学習課へのお問い合わせ



















